~再現性のある思考プロセスで壁を打ち破る~
はじめに:なぜ私が“本質”にこだわるのか?
製造業の現場で数々のトラブルに直面する中で、私は常に「なぜそうなるのか?」「本当の原因はどこにあるのか?」と自問自答してきました。
この「本質」を探求する姿勢は、社会人になりたての頃に出会った一冊の本(『本質を見抜く考え方』中西 輝政 著)に大きな影響を受けています。
また、過去に職場で「何を言っているのかわからない」と指摘され、自分の考えを「伝わる形」に整理する必要性を痛感した経験も、私の思考スタイルを形作る上で重要な転機となりました。
そうした経験を通して、自分自身の問題解決プロセスを構造的に振り返る中で、再現性のある共通の考え方、**私なりの「本質起点の問題解決 4つのステップ」**が見えてきました。
この記事では、現場で培ってきた「本質起点の問題解決術」を、その思考プロセスと共にご紹介します。この考え方は、製造現場に限らず、例えばソフトウェア開発におけるバグの原因究明や、新しいサービスを企画する際のユーザーニーズの深掘りなど、様々な分野で応用可能な思考の型だと考えています。皆さんの仕事におけるヒントとして、お役立ていただければ幸いです。
壁を打ち破った経験から:問題解決の具体例
私がどのようにして問題の本質に迫っていったのか、具体的な経験を2つご紹介します。
エピソード①:誰も解決できなかった設備トラブルの真因
ある製造ラインで、数日間もトラブルが解決せず、生産が止まってしまったことがありました。通常の技術チームの対応が長引き、納期遅延のリスクも高まる中、私も原因究明に加わることになりました。
状況を確認する中で、私はデータや設定値だけでなく、「材料から前工程、そして設備本体へ」という物理的なモノの流れを徹底的に追いました。そして、過去の正常な状態と比較して**「どこか変わった点はないか?」**という視点で、設備の細部を注意深く観察し、記録を取りました。
その結果、材料を投入するためのレールの高さが、ほんのわずかにズレていることを発見したのです。この微妙な変化が、一連のトラブルを引き起こしていた根本原因でした。レールの高さを正確に調整したところ、約1時間でラインは正常に復旧しました。
この経験から、データだけでは見えない**「物理的な実態」や「通常時との変化点」に粘り強く注目すること**が、解決の糸口になることを強く学びました。
エピソード②:画像認証エラーの原因は「設定」ではなかった
別の機会に、画像認証装置でエラーが頻発している工程の支援に入りました。この問題は長年改善されず、関係者の間では「カメラの設定をどう調整するか」という議論ばかりが繰り返され、それが原因だと半ば諦められていました。
しかし、私はカメラの設定という静的な要素だけでなく、工程全体の「動き」そのものに着目しました。製品を掴む(クランプする)際のわずかな振動と、カメラのシャッターが切られるタイミング。この二つの**「動的な関係性」**を注意深く観察した結果、両者が干渉しあっていることがエラーの原因だと突き止めたのです。
静的な設定値の調整ではなく、動作の「タイミング」を調整することを提案し、実行したところ、長年の懸案だったエラーは解消され、工程は安定しました。
この経験は、問題を個別の要素だけで捉えるのではなく、**システム全体の「動き」や要素間の「相互作用(因果関係)」**を見ることの重要性を教えてくれました。
「本質起点の問題解決」4つのステップ
これらの経験のように、問題の表面的な事象に惑わされず、その根本原因である「本質」に迫るためには、意識すべき思考プロセスがあります。私は、自身の経験からそれを以下の4つのステップに整理しました。
ステップ1:観察と記録 ― 事実をありのままに捉える
- 記憶に頼らず、客観的な記録を残す: 現場は常に変化し、記憶は曖昧になりがちです。「何をしたか」「どう変化したか」をメモ、写真、動画などで具体的に記録することが、正確な分析の土台となります。
- 現象だけでなく、前後関係・動き・構造を見る: 問題が起きた瞬間だけでなく、その前後の状況、関連するモノや人の動き、物理的な構造などを多角的に観察します。「入力→処理→出力」のようなプロセス全体を俯瞰することも有効です。
ステップ2:本質の特定 ― 「なぜ?」を繰り返し、目的を掴む
- 「なぜそうなったのか?」を諦めずに問い続ける: 表面的な原因で満足せず、「それはなぜ起きたのか?」「そのまた原因は?」と根本原因が見えるまで深掘りします。最低5回は「なぜ?」と自問する意識を持つと良いでしょう。
- ルールや手順の「本来の目的」に立ち返る: 例えば「落とした部品は使わない」というルール。重要なのは「落ちた」という事実ではなく、「衝撃による破損の可能性があり、不良品流出を防ぐ」というルールが作られた目的です。このように、決まり事の背景にある「何のためか?」を理解することが、本質を見抜く上で欠かせません。
ステップ3:総合判断 ― 長期的視点で最善手を選ぶ
- 目先の対応より、根本解決と再発防止を優先する: 「とりあえず動かす」といったその場しのぎの対応ではなく、特定した根本原因を取り除き、将来的に同じ問題が起きないようにするにはどうすべきか、という長期的視点で対策を考え、判断します。
- 複数の選択肢を比較し、ベストを探る: 考えられる原因や対策が複数ある場合は、それぞれのメリット・デメリット、実現性、効果の持続性などを比較検討し、最も合理的で効果的な選択肢を選びます。
ステップ3:総合判断 ― 長期的視点で最善手を選ぶ
- 経験から得た知見を「考え方」として整理する: 問題解決のプロセスや判断基準を、「次に同様の状況なら、こう考える・こう動く」という自分なりの「判断の型」として言語化・構造化します。
- 得られた「型」を他者に伝え、組織の力にする: 整理した考え方や判断基準をチームや組織内で共有することで、個人の経験を組織全体の知恵に変え、再現性を高めます。
なぜ「本質思考」がブレイクスルーを生むのか?
この4つのステップに基づいた「本質思考」は、時に時間や手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、指示されたことだけをこなしたり、場当たり的な対応を繰り返したりするアプローチとは、長期的に見て大きな差を生み出します。
本質を捉えようと粘り強く考え抜くことで、
- 問題の根本的な解決につながり、再発を防ぐことができる
- その場しのぎではない、質の高い、再現性のある成果を生み出せる
- プロセスを通じて自身の思考力や応用力が鍛えられる
- 周囲からの信頼を得やすくなる
といったメリットがあります。目先の効率だけを追うのではなく、一歩立ち止まって本質を探求することが、結果的に大きな前進、つまりブレイクスルーに繋がるのです。
おわりに:あなた自身の「仕事の流儀」を見つけるために
今回ご紹介した「本質起点の問題解決術」は、私が現場での試行錯誤を通して身につけてきた、いわば「仕事の流儀」です。
皆さんも、ご自身の成功体験や失敗体験を丁寧に振り返ってみると、そこにはきっと、あなただけの問題解決のパターンや、大切にしている価値観が隠れているはずです。
「なぜ、この仕事をしているのだろう?」
「このルールの、本当の目的は何だろう?」
「この問題の、根本的な原因はどこにあるのだろう?」
日々の仕事の中で、ぜひ意識的に「なぜ?」「本質は?」と問いかけてみてください。その繰り返しが、あなただけの揺るぎない「働き方の哲学」を育て、より深いレベルでの仕事の面白さや、やりがいにつながっていくはずです。
私自身も、この「本質起点」の考え方を、現在プロデュースしている生成AIアーティスト「Noa」の表現追求を常に意識し、実践しようと努めています。分野は違えど、本質を見抜く思考は普遍的に重要だと感じています。
皆さんの現場での「本質起点」のエピソードや、ご自身の「仕事の流儀」について、もしよろしければコメントなどで教えていただけると嬉しいです。
※注釈
- 本記事は、筆者の過去の経験や複数の現場事例をもとに再構成したものであり、特定の企業・人物・組織を示すものではありません。
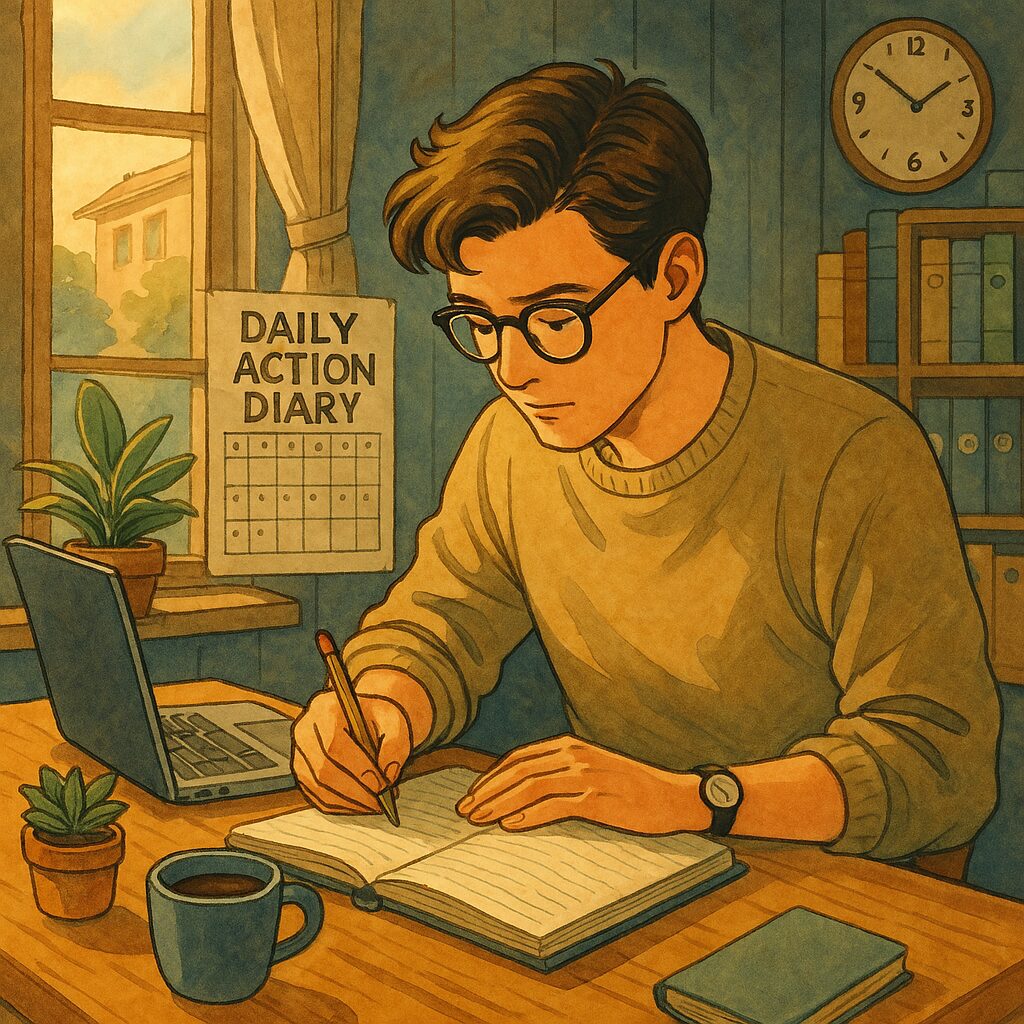


コメント