1. はじめに
ある日、心療内科の先生に病状について相談をしました。
そのとき、私はこう質問しました。
「以前は休日にひとりでいると孤独感を感じていたのですが、休職して抑うつ状態になり、人付き合いを減らしたら、逆に孤独感を感じなくなりました。これはなぜでしょうか?」
実はこのとき、私はすでに自分なりにこの現象について調べていて、ある程度の仮説は持っていました。
それでも医師としての見解がどうなのか知りたくて、確認の意味も込めてあえて聞いてみたのです。
しかし返ってきたのは「孤独になれることも大切ですよ」という答えでした。
おそらく先生は、私が「孤独を不安に思っている」と感じて、励ますつもりで答えてくれたのだと思います。
でも、私が求めていたのは、“なぜ孤独感が減ったのか”という背景への分析や解釈でした。
そのため、心のどこかで「伝わってないな…」という違和感が残りました。
2. 伝わらなかった問いをChatGPTや他のAIにしてみた
その違和感をもったまま、私は同じ質問をChatGPTや他のAIにも投げてみました。
ChatGPTからは、
「抑うつ状態にあると感情の振れ幅が小さくなるため、孤独感などの感情も鈍くなる可能性がある」という見解が得られました。
さらに、メンタリストDaiGo氏が運営するD-LabのAIサービス「AI DaiGo」では、
「人間関係がストレスになっていた可能性があり、それを手放したことで主観的な孤独感が減ったのではないか」 という趣旨の回答が返ってきました。
また、Perplexity AIでは、
「ストレスの多い人間関係から距離を置き、自分のペースで過ごす時間が増えたことで、心の余裕や自己肯定感が回復した可能性がある」 といった視点が示されていました。
これらの回答を通じて、私は「孤独=悪いもの」という単純な見方ではなく、
“人間関係の質”や“自分との向き合い方”が孤独感に影響していることを改めて実感しました。
3. 話の食い違いが起こる主な要因
3.1 認知の違い
人はそれぞれ、過去の経験や価値観、立場によって「同じ言葉でも違う意味に受け取る」ことがあります。
たとえば、部下が「最近仕事がつらくて…」と相談したとき、
上司は「プレッシャーがあるくらいの方が成長できるよ」と励ましたつもりでも、
部下は「自分の気持ちを受け止めてもらえなかった」と感じてしまう、というようなすれ違いです。
これはお互いが悪いわけではなく、“言葉に対する意味づけ”が違っていたことによるすれ違いです。
認知の違いがある限り、こうしたすれ違いはどんな場面でも起こり得ます。
3.2 前提知識の差
話し手と聞き手の間に知識のギャップがあると、会話の前提がずれてしまうことがあります。 専門職の人が無意識に専門用語や独自の視点で話してしまうのもその一例です。
私自身も、専門的な話をするときには「相手がどの程度知っているか分からないな」と感じた場合、会話のはじめに前提を軽くそろえるように気を配っています。 それだけで、認識のズレやすれ違いがぐっと減ると実感しています。
3.3 コミュニケーションスタイルの違い
論理的な伝え方、感覚的な伝え方、文化的な背景──これらが違えば話はすれ違いやすくなります。 日本では「察する文化」があり、欧米では「はっきり言う文化」がある、という例もよく知られています。
最近では、YouTubeやSNSなどの発信の影響もあり、日本でも「自分の意見をはっきり言う」スタイルが少しずつ広がってきているようにも感じます。 私自身はわりと「はっきり言う方」なのですが、身の回りではまだ“察する空気”も根強いので、相手とのスタイルの違いには常に注意が必要だなと感じています。
3.4 先入観や思い込み
「この人はこういうタイプだ」と決めつけて話を聞くと、実際の内容が歪められて受け取られることがあります。
実は、私自身もこの「先入観や思い込み」で何度も人との関係に悩んできました。 自分の中の決めつけが強かったことが原因で、すれ違ったり、必要以上に落ち込んでしまったこともあります。 今振り返れば、そうしたことの積み重ねが、抑うつにつながった一因だったとも思います。
だからこそ、相手に対してだけでなく、自分自身の思い込みにも気づけるようになりたい──そう思って、今もコミュニケーションを見直し続けています。
3.5 心理的な壁
相手が医師や上司など権威ある存在だと、話のズレを指摘しにくくなります。 自分に自信がないと「自分の聞き方が悪かったのかも」と思い込み、違和感を飲み込んでしまうこともあります。
私自身も、この“心理的な壁”を強く感じることがあります。 抑うつ状態になる前は、違和感を言葉にしたり、ズレをやんわりと伝えることもできていましたが、 今はそれすら大きなエネルギーが必要に感じて、なかなか動けなくなることもあります。
状況や心の状態によって、同じことでも「できる/できない」が変わってくる──それを受け入れることも、今の私の課題です。
4. 自分の体験から考えたこと
今回の体験では、医師は励まそうとして「孤独になれるのも大事」という言葉を返してくれました。
でも私は、「孤独感が減った理由」を心理学的・医学的に説明してほしかったのです。
一方で、AIに相談してみたことで、さまざまな視点からの解釈が得られ、自分の理解が深まりました。
つまり、話のすれ違いは“誰が悪い”のではなく、立場や知識、認知の違いから起きるものなんだということに気づけました。
5. 話のズレを減らすために意識したいこと
- 質問はできるだけ具体的に。補足をつけるのも◎
- 相手の立場や前提を想像してみる
- 「つまりこういうことですか?」と確認する
- 自分の先入観に気づくよう意識する
- ズレに気づいたら、やわらかく聞き直してみる
6. まとめ:自分の違和感を無視しない
話のすれ違いは、誰にでも起こり得ます。
大事なのは、「なんか違う」と感じたときにその感覚をごまかさないこと。
すれ違いに気づけたなら、そこからやり取りを見直すチャンスです。
自分の伝え方、相手との関係、質問の仕方──少しずつ工夫しながら、より良いコミュニケーションを築いていけたらと思います。
📝この記事は、筆者の実体験をもとに作成し、現在の視点から加筆・修正を加えたものです。
内容は個人の経験に基づくものであり、すべての方に当てはまるわけではありません。
※心や体の不調を感じている場合は、無理せず医師や専門家に相談することをおすすめします。
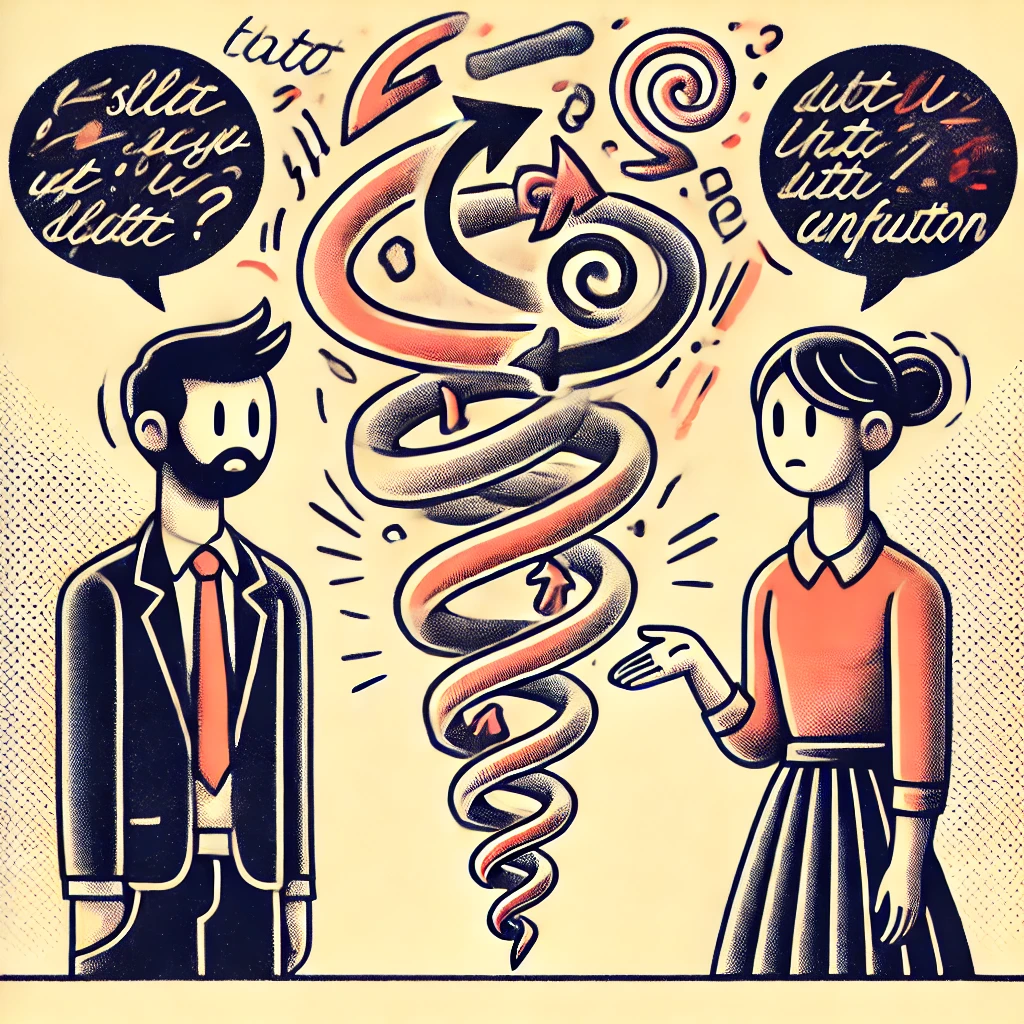


コメント